病気療養中で恒常的あるいは定期的な入院を必要とする子どもたちに、どうすれば学びの機会を届けることができるか――とても難しく、ひと筋縄には行かない課題です。実際にいま、子どもたちは病室で、あるいは院内の教室で、どのような学びの機会を得ているのでしょうか。そこには、子どもたちを支えたい、子どもたちの可能性を切り拓きたいという思いを原動力に、医療関係者との密な連携を繰り返しながら、そして最先端のICTツールも取り入れながら実践を積み重ねる先生がたの日夜にわたるチャレンジがあります。
Ed-tech総研では今回、「地域の小学校や中学校に通学できない児童・生徒が、病気を治しながら学ぶ学校」である大阪府立羽曳野支援学校を訪ね、東野校長と大林先生にお話を伺いました。
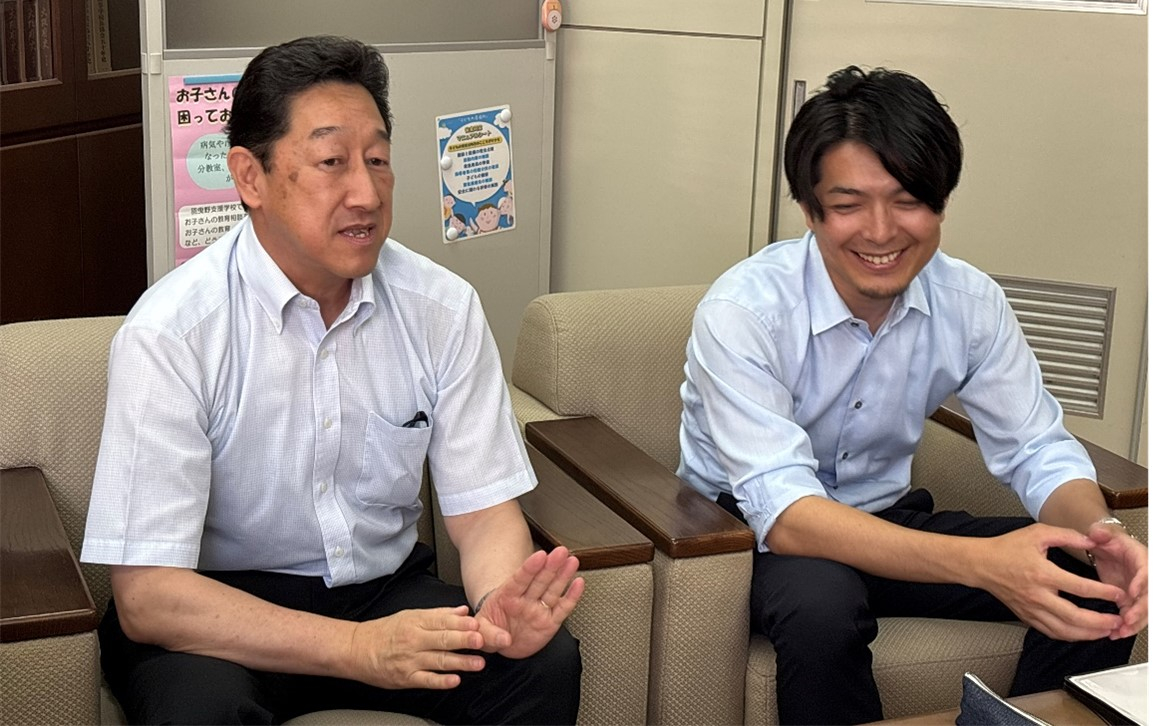
【大阪府立羽曳野支援学校・東野裕治 校長(左) 大林洋平 先生(右)】
病室から始まる学びの日常
――まず、羽曳野支援学校がどのような教育機関であるか、お聞かせください。どのような医療機関と連携し、児童・生徒のみなさんはどのような状況で学んでいるのでしょうか?
東野校長: 大阪府立羽曳野支援学校は、病気療養中の子どもたちに教育機会を提供しています。児童・生徒の約9割は、連携する病院内に設置された「分教室」や、病院への教員派遣による「訪問教育」によって学んでいます。具体的には、本校に隣接する大阪はびきの医療センターと、大阪母子医療センター、阪南病院、大阪労災病院など6つの分教室が設置されており、これらの病院に入院する子どもたちが教育を受けています。訪問教育は、大阪府内の他の病院に入院する子どもたちを対象に、週3日、1回あたり2時間で実施されます。
大林先生: 児童・生徒の在籍期間は非常に短く、平均して数週間から1ヶ月程度が多いですね。これは医療の進歩により、入院期間が短期化している傾向があるためです。このため、年間を通じて約300~400人もの転入・転出が繰り返されるという、教育機関としては極めて高い流動性を持つことが特徴です。
――年間300~400人もの児童・生徒のみなさんが入れ替わるとのことですが、この高い流動性の中で、先生方はどのように個別の学習に対応されているのでしょうか?
大林先生: 授業形態は、病室でのベッドサイド指導や、病院が用意した小規模な学習スペースでの個別指導が主となります。児童・生徒はそれぞれの元の在籍校から転校してくるため、学習進度や使用している教科書(出版社)が異なることが日常的に発生します。一人の教員が複数の教科書や進度に対応する必要があり、個別最適化された指導が求められる、という難しさがあります。
ICTも活用し切り拓く「小さな声」の表現
――羽曳野支援学校では支援にあたってICT機器の活用が不可欠なツールになっていると伺いました。具体的にどのような点で不可欠と感じていますか?
大林先生: 特にiPadのようなタブレットは革命的なツールとして高く評価しており、その携帯性と多様なアプリを活用できる特性から、ベッドサイドでの授業は100%タブレットを用いて行われています。これにより、教材の持ち運びが容易になり、写真や動画を駆使した多様な学習内容が児童・生徒一人ひとりのもとに届けられています。
――子どもたちが、ICT機器を通してどのように意思を伝え、学びを深めているのか、具体的なエピソードがあれば教えてください。
東野校長: 羽曳野支援学校の児童・生徒の病状の特性上、視線入力装置のような高度な意思伝達装置が頻繁に使われることはありませんが、軽度な力で操作できるボタンやタッチパネル式のタブレット、各種支援グッズは肢体不自由や重度・重複障害を伴う児童・生徒の学習支援に活用されています。
そして、ICTがもたらす感動的な発見の一つが、児童・生徒たちの秘められた能力の開花です。私の聞いた話で、以前の羽曳野支援学校で脳性麻痺により乳児期から長期入院をしていた生徒がいまして、それまで、文字を理解していないと思われていたその子は、タブレット(当時iPadの第3世代)を導入したことで、ひらがな入力ができるようになったという事がありました。
そこで大変驚くべきことに、その子は「ありがとう」といった自分の意思を文章にして伝えられるような能力があることを発見できたのです。これはその子が中学2年生の時の出来事で、もう10年以上も前のことですが、今でも話を聞いた当時の驚きを鮮明に覚えています。もしiPadが発明されていなかったら、その子が文章を打ってコミュニケーションできるということが、もしかしたら永遠に分からなかったかもしれない。機器の進歩により子どもたちの能力がより現れやすくなったと、この時強く実感しました。そしてこの時の発見は、私たち指導者だけでなく、生徒本人と周囲の大人たちにも大きな喜びと希望を与えました。周りの大人がそういう潜在能力に気づくことで、児童・生徒の可能性をどれほど引き出す事ができるか、大きく変わってきます。そう考えるとICTの力は計り知れないと感じます。
大林先生: ICTは学習支援に留まらず、子どもたちの交流の可能性も大きく広げています。長期間病院の外に出ることができない子どもたちが、オンラインで元の学校の学級活動に参加できた際に大きな喜びを感じていた、というシーンがありました。
これは、物理的な距離を超えて、つながることの尊さとそれが子どもたちの心にもたらすポジティブな影響が鮮明に現れています。遠方から入院している子どもたち(群馬県や千葉県、徳島県など大阪以外から来る子も多い)にとっては、元の学校のクラスメイトや先生と話す機会は非常に少ないものです。ですが、ICT機器を使うことにより元の学校のクラスの授業にオンラインで一緒に参加・交流する機会を多くつくることができるようになました。また、学校だけでなく、分教室間をオンラインで繋いだ学習発表会やクイズ大会、修学旅行などを実施することで、治療しながらも子どもたち同士が活発に交流できるようにしています。こうした交流は、「自分だけじゃない」「もっと頑張れる」という安心感や活力を育み、子どもたちの精神的な支えともなっています。
以前は物理的に不可能だったことが、ICTを活用することで可能になり、子どもたちも日々楽しんで学習に取り組めています。
――医療機器との干渉など、ICT導入における課題はどのように乗り越えていますか?
大林先生: 医療機器への影響や病室のプライバシーの問題から、ネットワーク機器の制限や、多人数での同時参加が難しいといった課題も存在します。病室の多くは4人部屋なので、1人に授業をしていても、他の3人に聞こえてしまうという課題もあります。しかし、病院側と連携し、一時的にネット環境の整った部屋を借りて交流を深めるなどの工夫も凝らしています。また、児童精神科の分教室では、児童・生徒の行動レベルを医療スタッフと学校教員が連携して設定し、このレベルに応じてICT機器の利用や活動内容を決めることで、治療への影響を最小限に抑えながら活用しています。
東野校長: 私たちの教育現場は、何よりも優先されるのは治療です。治療優先が大前提であり、学校の行事や授業は、生徒の治療を邪魔しないように細心の注意を払って計画されます。だからこそ、私たちはICT機器の使い方を常に工夫しています。
多くの機器がある中で、それをどのように児童・生徒の学びと交流のために最大限に活用できるか、それが私たちのチャレンジです。
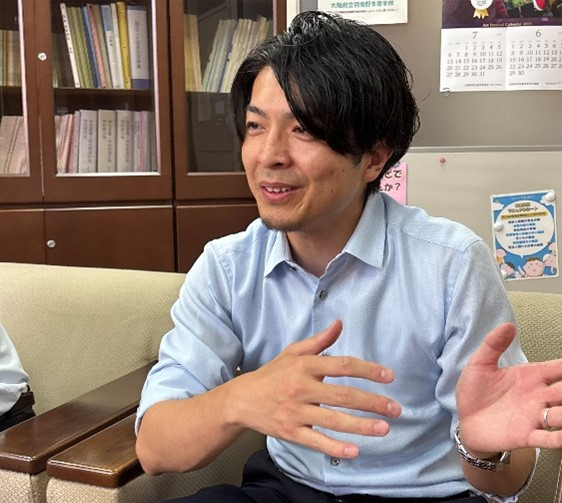
学習を超えるテクノロジーの力
――ICTの活用は、単なる学習だけでなく、児童・生徒のみなさんの「楽しさ」や「喜び」といった感情を引き出す上でも役立っていると伺いました。具体的にどのような取り組みがありますか?
大林先生: 入院中の子どもたちが社会とのつながりを持ち、様々な体験ができるよう、オンライン交流を盛んに行っています。また、病院の外に出られない子どもたちのために、360度カメラやVRヘッドセットを活用した「疑似体験」も提供しています。例えば、教員が万博会場に360度カメラを持って行き、その映像をVRで体験させる試みが進行中です。さらに、ベビーモニターのカメラを応用し、遠隔でボッチャというスポーツの対戦を行うなど、既存の技術を創造的に活用したユニークな取り組みも行っています。これにより、場所や時間の制約、手先の不自由さがクリアされ、子どもたちの「できた!」という実感を促しています。
――芸術・音楽教育においてもICTが活躍されているとのことですが、具体的にはどのような取り組みですか?
大林先生: 病院という環境では、使用できるものに多くの制限があります。例えば、絵の具や粘土の使用にはアレルギー物質(例:小麦)の厳密な確認が必要です。また、理科の実験器具や生物を見せる際にも土の使用が禁止されるなど、様々な制約があります。ICT、特にタブレットやパソコンを活用することで、これらの物理的な制約を乗り越えています。例えば、タブレットを使って絵の具で絵を描いたり、実験の様子を体験したりすることが可能です。
音楽教育においては、身体の制約により楽器に触ることが難しい児童・生徒もいます。また、病院という場所の特性上、楽器を持ち込めなかったり、大きな音が出せなかったりする制約もあります。これらの課題に対し、様々な音楽関係のICT機器を導入・活用しています。例えば、iPadを操作することでギターの音を鳴らしたりするような活用がされています。これにより、今までできなかったことがICTの活用によって可能になり、アートや音楽療法といった分野でも高い効果を上げています。
また、書道の授業も行っていますが、これは墨汁ではなく水を使って書く商品を活用しており、病院内での汚れやアレルギーのリスクを避けています。可能な場合はICTだけでなく、実際に体験できるものについては、極力触って体験させる取り組みも同時に行っています。
命を守り、学びを支えるチーム支援
――病弱教育において、医療機関との連携は最も重要な要素の一つと考えます。医師、看護師、リハビリテーション専門職、心理士、そして教員の方々が、どのように連携して子どもたちを支援しているのでしょうか?
東野校長:児童・生徒が転入する際には、必ず医師からの医療所見を受け取り、教員全員でその内容を共有します。特に重篤な疾患を持つ児童・生徒については毎朝、医療関係者(医師、看護師、心理士、PT、OTなど)と教員による詳細なミーティングが約20~30分間行われ、その日の児童・生徒の体調や精神状態、治療状況に応じた指導内容を調整しています。これにより、安全を確保し、治療を妨げない教育活動が実現されています。また、医療との連携を深めるため、教員が人工呼吸器に関する研修を受けるなど、医療知識の習得も行っています。これにより、児童・生徒の体調変化をより深く理解し、教員も適切な対応ができるよう努めています。
――児童・生徒のみなさんが退院する際の「退院前地域校カンファレンス」について、その目的と具体的な内容を教えてください。
大林先生: 児童・生徒が退院する際には、地域の学校の教員、保護者、医療関係者、そして羽曳野支援学校の教員が参加する「退院前地域校カンファレンス」が開催されます。ここでは、入院中の学習状況や生活面での支援方法、退院後の注意点などが共有され、児童・生徒がスムーズに元の学校生活に戻れるよう、多角的な視点から支援が行われています。また、近年では入院前から不登校傾向がある子どもも多く、そういった子どもたちが、スムーズに元の学校生活に戻れるよう、サポートする場でもあります。
東野校長: 分教室に通うことで、手厚い学習環境が提供されます。場所、人、動き、時間の制約のある子どもたちがICTを活用することで、「できた!」という実感を持ち、それが自信となって元の学校に戻っていける。これこそが、教育環境の格差を解消し、全ての子どもたちに学ぶ喜びと生きる希望を届けることに繋がっていると考えています。

地域と未来をつなぐ挑戦
――新しい取り組みやプロジェクトの計画など、今後の展望についてお聞かせください。
東野校長: 羽曳野支援学校が持つリソースを最大限に活用し、地域の子どもたちへの支援を広げるための新たな2つのプロジェクトを構想・推進しています。
一つ目は「出張型学びの支援」です。これは人間関係のつまずきや学習困難から不登校になり始めた子どもたちを対象に、専門的なアセスメントと個別トレーニングの支援方法等を提供し、不登校の未然防止を目指すものです。具体的には、発達の凸凹を確認し、文字の読み書きの困難さへのトレーニング、聴覚情報の集中力向上プログラム、SST(ソーシャルスキルトレーニング)による人間関係の改善支援などを行います。豊富な教員リソースを地域の子どもたちの支援に活用することで、年間数万人と言われる不登校児童・生徒の数を1%でも減らすことができれば、大きな社会貢献につながると考えています。このプロジェクトは、最近、羽曳野市教育委員会との協議がまとまり、今夏から具体的な取り組みが開始される予定です。
二つ目は「オンライン学習機器の貸し出しと活用支援」です。ICT活用に不慣れな地域の小中学校や病院に対し、オンライン授業に必要なカメラセットや通信機器を貸し出し、その設定・運用をサポートすることで、オンライン学習の普及と定着を促進します。学校独自のマニュアルを作成し、教員が学校を訪問して機器のセッティングを支援する予定です。退院間近の生徒が、退院前に360度カメラを使って元の学校の様子を確認できるような取り組みも検討されており、社会復帰への不安軽減を目指しています。これらをモデルケースとして他の地域にも展開し、病弱教育における知見を広く共有することで、全国的な教育支援の向上に貢献したいと考えています。
――最後に、お二人が子どもたちの支援を今のような形で行うに至った経緯や経験をお聞かせください。
大林先生: 私(大林先生)自身は、元々このようなたいそうな志を持って教員になったわけではありません。しかし、病弱の支援学校に赴任し、初めてこのような学校や子供たちがいることを知り、発達障害や不登校、病院での制約がある子たちと関わる中で、「自分に何ができるのか」を考えるようになりました。自分の強みであるICTを活かして、彼らの支援に取り組んでいます。
東野校長: 私(東野校長)は教員になって40年以上になります。元々はパイロットになりたかったのですが、視力の問題で断念し教員を選びました。どの仕事であれ、真剣に向き合えばきっとその仕事でしか得られない境地に誰でもなると私は思います。
教師の仕事は、自分が支援することで子どもたちが成長するのを毎日、間近で見られる仕事です。児童・生徒が困難を克服し、喜び、成長していく姿を見ることは、私たちにとって大きな喜びであり、「やれる範囲の中で何ができるか」を自然と考えるのが教員としての役割だと考えています。校長として、与えられたリソースや設備、そして先生方と共に、子どもたちにより良い教育環境を提供するために何ができるかを常に考えています。

担当者として感じたこと 〜大阪府羽曳野支援学校を取材して~
今回の取材を通して、病と闘いながらも学ぶことを諦めない子どもたち、そしてその子どもたち一人ひとりに真摯に向き合う羽曳野支援学校の先生方の情熱に深く心を打たれました。東野校長と大林先生が最後に語ってくださった「どんな仕事であれ真剣に向き合えば、他者の成長や喜びに貢献できる」という強い信念は、まさにこの学校の教育現場で体現されていると感じました。
羽曳野支援学校の取り組みは、単に知識を教えるだけでなく、子どもたちの心と生きる力を育む人間教育そのものです。ICTというテクノロジーが、病室という限られた空間の中で、子どもたちの小さな声を拾い上げ、コミュニケーションや自己表現の可能性を無限に広げていました。オンラインでの交流を通じて「自分だけじゃない、もっと頑張れる」という安心感や活力を得ていく子どもたちの姿は、私たちに大きな希望を与えてくれます。
医療機関との緊密な連携、そして不登校問題への新たな挑戦は、教育環境の格差を解消し、全ての子どもたちに学ぶ喜びと生きる希望を届け、まさに可能性を切り拓いてく取り組みであると感じました。

