近年、小中学生から高校生、そして大学に至るまで、学生を取り巻く環境は大きく変化しています。特に学生の多様化が急速に進む日本の大学教育において、個々の学生に寄り添った支援のあり方が問われています。こうした背景の中、関西国際大学の中嶌康二准教授とリクルートEd-tech総研の森崎晃は協働し実践研究を進めてきました。具体的には、大学に蓄積された、学習や学習以外の活動に関する各種データを解析することで、個別の支援に活かすことができないか――というものです。今般、その一次成果が「学習活動ログに基づいて早期支援が必要な学生を判別する教員支援方略の提案」というタイトルで公開されました。本対談では、同内容を深掘りする形でのインタビューを実施し、ICTツールや学習ログデータを活用した早期支援が必要な学生の判別と教員支援方略について、その挑戦と展望を語り合いました。
論文のリンクはこちら
リクルートEd-tech総研・森崎晃(左)関西国際大学社会学部・中嶌康二准教授/評価センター長(右)
大学教育を取り巻く「多様化」の波
―――まず、大学において学生の支援上、どのような課題が発生しているかお伺いします。学問の教授以外にも、教員が取り組むべき課題があるとお聞きしました。具体的にどのような課題があるのでしょうか
中嶌先生:一言で言えば、学生が非常に多様化しています。学力の多様化はもちろんですが、従来型の教室での対面授業では学びにくい学生が増えています。人とのつながりやグループワークに難しさを感じる学生もいれば、授業中のノートテイキングなど個別サポートが必要なケースも多いです。モチベーションのばらつきも顕著です。加えて、この2、3年で留学生が増加し、出身国も多様化しています。以前はアジア中心でしたが、現在はインドネシア、バングラディッシュ、ネパールなど南アジアからの学生も増え、一つの教室の中に本当に多様な学習者が共に学んでいるのが現在の状況です。一つの教室の中に多様な学習者がいる中で、大学として教育・学習の質を担保する必要があります。
中嶌先生:また、コロナ禍は多様な学び方を許容するきっかけとなりましたが、その変化に教員側の準備や対応が追いついていない現状があります。さらに、2024年度からは合理的配慮の対応が義務化され、学生が学べる環境整備が大学に求められています。申請があれば委員会で対応を決定しますが、そこまでいかない「グレーゾーン」のケースも多く、現場での運用が難しいと感じています。情報が断片的で、教員一人ひとりが全ての学生の状況を把握することが難しい場合もあります。
森崎:高校の段階でも、通信制高校で学ぶ生徒が増加傾向にあり、彼らが大学に進学するケースも増えています。通信制高校の生徒は探究学習に長け、自由な余地が与えられると花開く傾向があります。しかし、従来の画一的な教育に慣れていないため、大学に入ってから戸惑うこともあります。
教える「仕組み」をデザインする
―――そのような多様化する学びに対応するために、中嶌先生のご専門である教育工学が重要になってくるのでしょうか。
中嶌先生:まさにその通りです。教育工学とは、教える「仕組み」を研究する分野です。ICTや情報学、教育学のアプローチが融合しており、学ぶための仕組みをデザインします。
特にインストラクショナルデザインは、日本ではまだあまり認知されていませんが、「教えたか」ではなく「学べたか」を重視する「学習者中心」の考え方を基盤としています。文部科学省も「学習者中心」を提唱していますが、従来の「教師主導型」の教育観が根強い中で、「学べたかどうか」で評価し、そのための授業設計を考えるのがインストラクショナルデザインです。
授業設計と聞くと、多くの教員は毎回の授業計画を想像しがちですが、学習者中心の発想では、最初に「目標」と「評価方法」を設定します。それをゴールとして、どのような授業を実施するかという順番で設計を進めます。小中学校には学習指導要領という明確な目標がありますが、大学教員は、担当科目の責任範囲を踏まえて自分で学習目標を設定しなければなりません。だからこそ、大学教員こそインストラクショナルデザインを学ぶべきだと考え、普及に努めています。
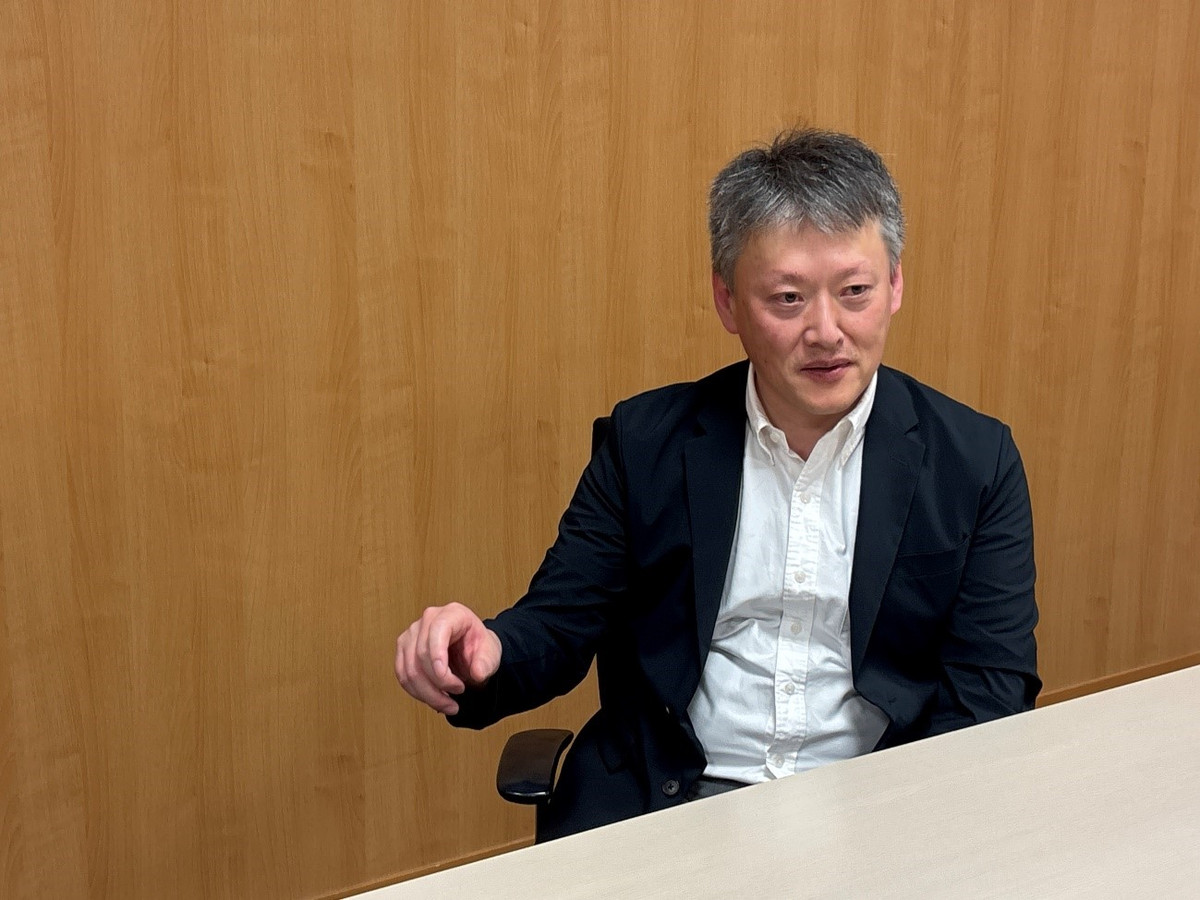
―――そうした課題意識の中で、関西国際大学は学習ログデータの活用に取り組んでいます。どのような具体的な取り組みを進めているのでしょうか。
中嶌先生:私たちは学習ログデータを分析し、支援が必要な学生を早期に発見し、適切なサポートをデザインすることを目指しています。しかし、既存システムのデータ連携は後手に回ったという反省があります。データ連携ができていないため、具体的な着手となると課題が山積していました。そこでリクルートEd-tech総研の森崎さんにお声がけさせていただきました。
森崎:上記の背景の中で中嶌先生にお声がけをいただき、リクルートEd-tech総研として参画させていただきました。私自身、これまで小中高生の学習履歴データから子どもの学習やメンタル面の変容を読み解く研究をしてきたので、その知見を大学生にも応用できるのではないかと考えたのが、この取り組みの始まりです。
中嶌先生:学習ログ活用の最大の目標は、「支援が必要な学生を早期に発見し、その状況に応じた適切なサポートをデザインすること」です。特に、「中途退学を防ぐためには、発見したあとの支援方略のデザインまでを視野に入れること」を第一に考えています。
森崎:本人が希望しない中途退学を防ぐためには、出席率が低いといった単純な要因だけでなく、複数のデータを複合的に見ています。具体的には、以下の3つの大きなカテゴリのデータを活用しようとしています。
・学習関連データ:講義の履修状況、学力、成績、出欠、提出物など。
・学内活動や帰属意識に関するデータ:部活動、サークル活動、オープンキャンパスの活動参加など、大学とのつながりや親しみを示す情報。
・入学時点からの状況:留学生であるか、特性(発達特性など)があるか、家庭の状況など。
関西国際大学は、教員も学長も、学生のデータをパネル形式でちゃんと蓄積している点で、他の大学と比べても優位性があります。私のバックグラウンドである不登校支援の経験からも、学習以外のデータ(相談回数、部活動、サークル活動、人間関係など)も活用し、子どもたちの「心の内面の変容」を図る総合的なアプローチへの関心が深いです。

教員の役割変革:「教授者」から「支援者」へ
―――このようなデータ活用を進める上で、教員側の難しさや負担はどのようなものがあるのでしょうか。
中嶌先生:大学の教員は皆忙しく、全学の教員研修会を企画する部局では、取り上げたい課題が多すぎて、優先順位付けや消化不良にならないように苦慮しています。新しい取り組みが増えることは良いことですが、それが教員にとって「業務が一個増えた」と感じられると、なかなか浸透しないと感じています。
森崎:そうですね。教員の方々は当然やっていきたいと考えていても、多忙な中で新たな業務を増やすことへの抵抗感は理解できます。
中嶌先生:まさにその通りです。多様な学習者が存在する教室に対応するため、大学教員にも授業担当者として必要とされるさまざまなスキルの「最低限の要件」が変化しつつあると感じています。大学側が研修やリソース提供でそれを支援し、補填する仕組みが必要です。教員の研究と学生支援業務がリンクすれば理想的ですが、「別の仕事」と捉えられると負担が大きいため、全員共通の責務とする場合は、レリバンスを高める方策が必要になるでしょう。
森崎:教員のモチベーションをデザインするためには、強固なエビデンスを示すことや、シンプルなポイントから始めることが重要だと思います。負担が軽く、かつ効果が見える具体的な打ち手を示すことで、主体的に動いてもらえるようにすることが鍵だと考えています。
中嶌先生:繰り返しになりますが、時代の流れの中で、大学教員に求められる「最低限の要件」が変わりつつあると感じています。教員の役割は、知識を一方的に伝える「Sage on the Stage(壇上の賢人)」から、学習者と同じフロアに降りて、その場で支える「Guide by the Side(傍らの支援者)」へシフトしています。このことから、多様化する学生に対応できるよう、大学が新たな研修機会を提供したり、リソースを補填できるような仕組みが必要だと問題提起をしていくつもりです。
理想の大学教育へ:未来に向けた教育の共創
―――関西国際大学は、今回の取り組みを含め、非常に積極的で革新的な印象を受けます。大学経営の視点から、その特徴や背景についてどうお考えですか。
森崎:関西国際大学は、少子化による大学進学者数の減少という、日本全体の大学が抱える「危機感」を非常に強く持っている点が特徴的です。この危機意識があるからこそ、積極的に様々な打ち手を講じることができるのだと感じています。大学経営は、学生や保護者を欺くことはできません。本当にその学生の人生の利益になる4年間を提供できるかを示すことが重要であり、関西国際大学は正攻法でその価値を示そうと努力していると言えると思います。
中嶌先生:本学の学長は、積極的に新しいアイデアを提案されます。我々教員はそれを受け止めて、本質を捉えたレスポンスを返す姿勢が求められます。建設的な議論を重ねながら、常に前に進もうとしています。こうした背景から、関西国際大学がクリエイティブで革新的な取り組みを推進しようとする姿勢が生まれるのだと思います。
―――最後に、今後の展望についてお聞かせください
中嶌先生:今後の目標としては、これまでの学習ログ分析から得られた知見を活かし、「支援を要する学習者」を予測し、その状況に適した個別支援方略を担当教員に提案する「教員支援フレームワーク」の設計・開発をさらに進めていきたいと考えています。またそのなかで、データと教育理論を融合した支援方略を提案し続けていきたいです。
森崎:私も、学習以外のデータも活用し、学生の心の内面の変容まで図るような総合的なアプローチを追求していきたいです。データと人間の対話を深めることで、問題が顕在化する前に支援を届け、子どもたち一人ひとりが自分の可能性を最大限に発揮できる社会を目指していきたいと考えています。
―――本日はお忙しいところありがとうございました。本研究の益々の発展をお祈り申し上げます。
取材・文/水谷伊吹



