1 はじめに
近年、小学校や中学校、そして高等学校の現場ではICT教材を活用し学ぶことが一般化しつつあります。その目的のひとつに個別最適な学びを実現し、基礎学力の定着を図ることで、子どもたちの進路の幅を狭めないようにすることが挙げられます。
しかし、この動きはなにも高等学校までの学齢期に限った話ではありません。本レポートでは、名古屋経営短期大学(愛知県尾張旭市)が取り組むICT教材の活用について取り上げます。
同学の子ども学科で准教授を務め、ICT教材を活用した学習支援の取り組みをリードする、大藏純子さんにお話を伺いました。
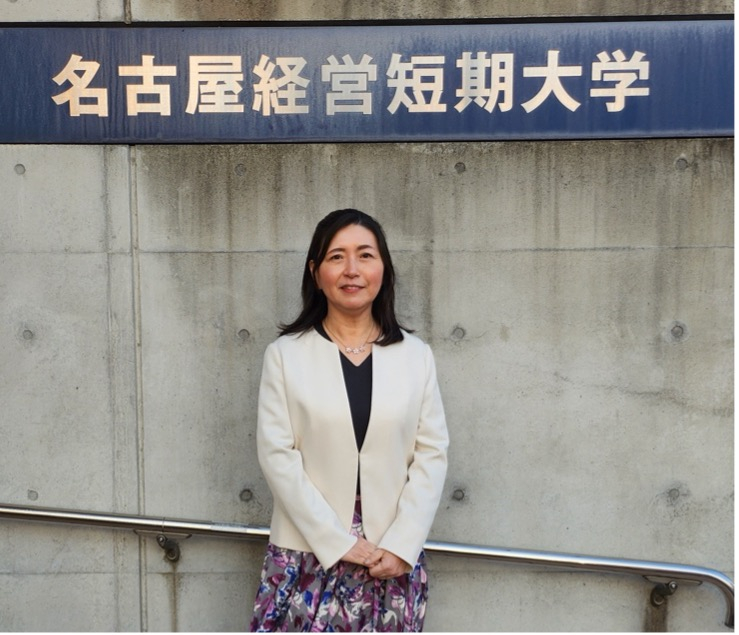 名古屋経営短期大学 准教授 大藏純子(おおくら・じゅんこ)さん。27年間の小学校教諭経験を経て2023年より現職。将来、小学校教諭や保育者として活躍したいと考える学生の教育に携わりながら、専門である道徳教育の研究活動にも従事している。
名古屋経営短期大学 准教授 大藏純子(おおくら・じゅんこ)さん。27年間の小学校教諭経験を経て2023年より現職。将来、小学校教諭や保育者として活躍したいと考える学生の教育に携わりながら、専門である道徳教育の研究活動にも従事している。
2 短期大学での学びや進路と基礎学力の重要性
――まずはどのような学科があり、卒業後にはどういった進路を描く学生がいるのか教えて下さい。
大蔵さん:名古屋経営短期大学には「未来キャリア学科」、「子ども学科」、「介護福祉学科」の3学科が設置されています。「未来キャリア学科」はビジネス情報フィールド、観光フィールド、医療事務フィールド、ビューティフィールドに分かれ、卒業後の進路・就職先もさまざまです。私も所属する「子ども学科」は多くの学生が小学校教諭あるいは保育士・幼稚園教諭を目指し、そして「介護福祉学科」は介護士などの福祉職を目指し勉強に励んでいます。ちなみに、「子ども学科」は愛知県内に所在する短期大学では唯一、3つの資格・免許を取得することのできる学科なんです。
――きょうは主に「子ども学科」について伺わせてください。授業や学び方にはどのような特徴がありますか。
大藏さん:まず、「子ども学科」では短期大学に一般的な2年度制ではなく、3年度制を敷いているという特徴があります。1年生では基礎科目を受講し基礎学力を含めた基礎的な力を身につけながら、後期からは専門科目を受講します。また、2年生や3年生では資格取得や就職を見据えた対策も行い、実践的な力を身につけます。3年間学ぶことのメリットとして、小学校教諭も保育者(保育士・幼稚園教諭)もいわば対人援助職ですから、理論と共に実践でも準備を積み重ねられることが挙げられます。さらに、保育者としては保育士資格と幼稚園教諭二種免許の双方を取得できるため、将来的に勤務できる場の選択肢が広がるというメリットもあります。
――短期大学の学生のみなさんは履修する講義が多く、忙しいと聞いていますが。
大藏さん:4年制大学と比べれば、2年間ないし3年間で学びきらねばならないため、どうしても履修講義数は多くなります。学年や学科にもよりますが、1日に1限から5限までびっしり、週5日でみても20コマ以上の講義を履修することも珍しくありません。そのような状況ではありますが、本学科では1学年あたり約30名の学生に対し、9名の専任教員が指導・支援にあたっていますので、教員間では「愛情教育」を合言葉としており、きめこまやかなサポート体制で運営しています。
――学生のみなさんの特徴を挙げるとすればどんなことが挙げられますか。
大藏さん:そうですね、私が受ける印象としては、おだやかで素直、やさしい学生が多いかなと思います。多くの学生が小学校教諭や保育士になりたくて入学してくることもあって、子どもが好きで、子どもたちのために働きたい、という心の持ち主ですので。実際に、学生同士のやりとりを見ていても、1学年あたり約30人という規模で距離感が近いこともあり「最近ちょっと元気ないんじゃない? なにかあったの、大丈夫?」なんて声かけをし合ったりもしていて、やさしい子たちだなあと感じます。
――学生のみなさんを指導・支援する中で、基礎学力の重要性を実感していると伺いました。
大蔵さん:そうなんです、みんな将来の夢に向かって頑張っているのですが、その実現にあたって基礎学力の不足がネックになってしまうケースがあるんです。近年では入学試験のあり方も多様化し、指定校推薦などの制度を活用することで、学力試験を経ず進学・入学する学生も少なくありません。そのため、構造上、勉強するという行為をあまり多くは経験してこなかったという実態もあります。しかし、いざ入学すると短期大学は4年制大学に比べて就職までの期間も短く、学んだことが将来の働くに直結しますし、対人援助職という性質上、正しい知識を持ち行動できねば現場に立つわけにはいきません。「こんなに勉強しないといけないなんて・・・」「勉強は苦手なので・・・」「どうやって勉強すればいいんだろう・・・」と戸惑ってしまう学生も多いです。中には(勉強が大変だし、もう諦めようかな・・・)なんて学生もいます。将来の夢を実現するにあたって、基礎学力の不足がネックになってしまうケースがあるのです。基礎学力の不足が進路選択の幅を狭めることがある、と言いかえてもいいかもしれません。とにかく、2年生以降の専門科目や就職対策のスタートラインに立つためにも、基礎学力の重要性は非常に高いのです。加えて、基礎学力の習得に挑む過程で、働くうえで大切な自尊感情や忍耐力を身につけることもできると考えています。

3 ICT教材を活用した基礎学力定着支援
――1年生の基礎科目の中で、ICT教材を用いた指導・支援を実践していると伺いました。
大藏さん:1年生で履修する、その名も「基礎学力講座Ⅰ・Ⅱ」という講座(演習)があり、これは卒業にあたって必修科目としています。資格取得や採用試験の突破、また就職後の業務遂行に必要な基礎学力を、主に高校生までの教科・単元内容から修得していこうというものです。かつてはプリントなどを用いた紙ベースでの学習スタイルでしたが、私が科目担当になってからICT教材の活用をはじめました。具体的には「スタディサプリ」という教材を使用しているのですが、学生一人ひとりの状況にあわせた学習環境を提供するうえで有効だと感じています。
――具体的な活用法についても教えてください。
大藏さん:「基礎学力講座Ⅰ・Ⅱ」は週に一度、ひとコマの開講なのですが(次年度からはふたコマとする計画もあります)、まずその初回ないし2回目までを使ってレディネスチェックテストを実施します。レディネスチェックテストは「到達度テスト」という名称なのですが、英語・数学・国語の各教科について、高校生履修範囲までの各単元の基礎問題がまんべんなく出題されるので、これを解くことで学生一人ひとりの得意や苦手、また到達度を把握できます。このテストを受検することで、正答状況に基づき一人ひとりにあわせた課題である「連動課題」も生成されます。また、教員からも「スタディサプリ」上でその1週間に取り組んでほしい課題を配信します。こちらは中学校や小学校の履修範囲も含まれています。以降の講義では、90分の授業のうち冒頭の30分で配信課題の内容を問う小テストを行い、残りの60分で連動課題を中心に各自が取り組むべき教科・単元を学んでいきます。こうした、学年をさかのぼって学ぶこと、苦手な箇所にピンポイントで取り組むことのできる個別最適な学習環境の提供は、やはり紙ベースの学習では難しく、ICT教材の利点だと感じています。
【基礎学力講座での、ICT教材活用法】
(1)レディネスチェック:初回授業で「到達度テスト」を受検することで、学生一人ひとりの習熟度を把握
(2)取り組み課題の提示:「到達度テスト」の結果を受け個別に生成される「連動課題」に加え、教員がシステム上にて週毎に課題を配信
(3)確認テストと個別最適な学び:以降の授業では、冒頭の30分で小テストを行い、残りの60分で各自の課題に取り組み
4 学生の変化や効果実感
――ICT教材を用いた取り組みを通して、学生のみなさんの変化や効果実感はありますか。
大藏さん:はい、変化や効果は様々な場面で感じています。まず学生の変化ですが、最初は嫌々取り組んでいる学生も多かったと思いますが(笑)、配信された課題の提出率もいまではほぼ100%ですし、授業を欠席するケースも大幅に減りました。授業の冒頭で行う小テストでは、最近では3人にひとりが満点を取るようになり、そうでない学生でも高得点を取るようになっています。基礎学力の範疇ですから、専門科目よりも努力が得点に結びつきやすく、「やればできる」という体験が積み重なって自信につながっているのだと思います。実際に、勉強が苦手だった学生がとうとうテストで満点をとることができて、うれし泣きをしたというシーンもありました。
――教員のみなさん側の変化や実感はどうですか。
大藏さん:教員側にも効果があったと感じています。もちろん学生の目標や夢の実現率を高めるためのこの取り組みに共感いただくことができているというのもあるのですが、それだけではありません。学生一人ひとりの学力や得意・苦手が可視化されたことで、教員にとって指導・支援するにあたって参照できる情報が増えた、ということが挙げられます。ある学生に対し専門科目を教えていても、その学生が講義内容を理解できているのかあるいはできていないのかがわからない、理解できていない場合はどこでつまずいているのかがわからないケースが以前は少なくなかったのですが、いまは「あ、そうか、国語が苦手だからつまずいているのか、伝え方を変えよう」ですとか「この子は算数・数学が苦手なのか、であればアプローチ方法を工夫しよう」といった工夫ができるようになりました。現在のところ、講義の中でICT教材を活用できているのは1年生向けの「基礎学力講座」のみですが、専門科目の教授に集中しなければならないというハードルはありつつも、2年生・3年生向けの講義にもICT教材を組み込むことができたらなあなんて考えてもいます。
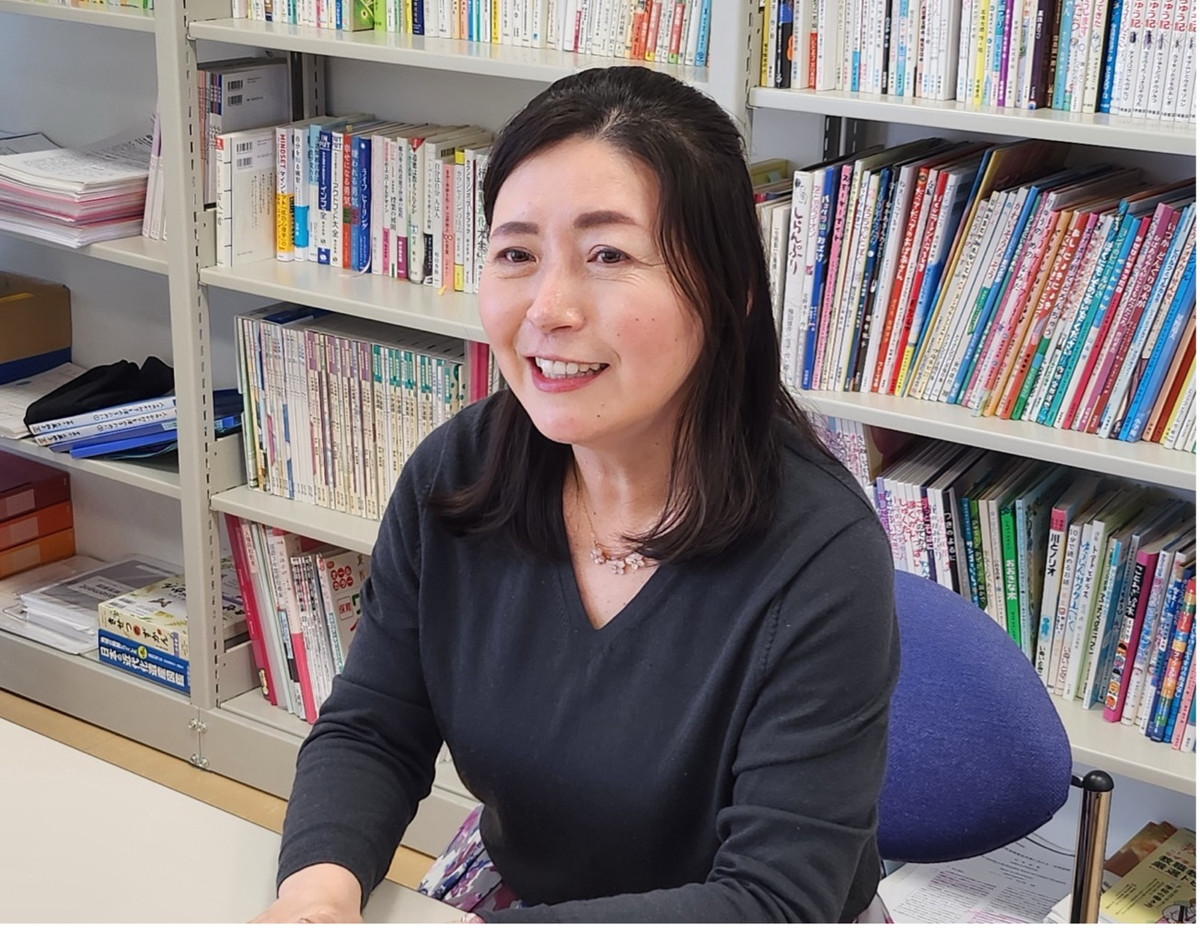
5 これからICT教材の活用に挑むみなさんへのメッセージ
――短期大学やさまざまな教育機関で、これからICT教材を活用した学生指導・支援に挑むみなさんに対しメッセージをお願いします。
大蔵さん:私はもともと小学校の教諭で、専門は当初は社会科(日本史)、その後は道徳へと移っていきました。いまは学生たちのサポートと、道徳教育の研究に没頭しています。対人援助職に就いていく学生たちに接していても、あるいは道徳教育について研究を行っていても、大切なことは結局、「人は人とどう関わっていくと幸せになることができるのか」ということなのではないかなと。専門科目を学び、資格試験や就職試験を乗り越えるためにも、また自ら問いを立て思考するためにも、その基盤として基礎学力は欠くことができません。その学びに有効なシーンも多いICT教材を活用することは、選択肢のひとつとして検討する価値があります。私は学生に対し、あきらめないこと、そして努力すること、このふたつを伝えたいといつも考えて取り組んでいますが、ICT教材の力も借りながら、それが学生自身の口から「伝わってきた」と言ってもらえる幸せな瞬間にも巡りあうことができました。
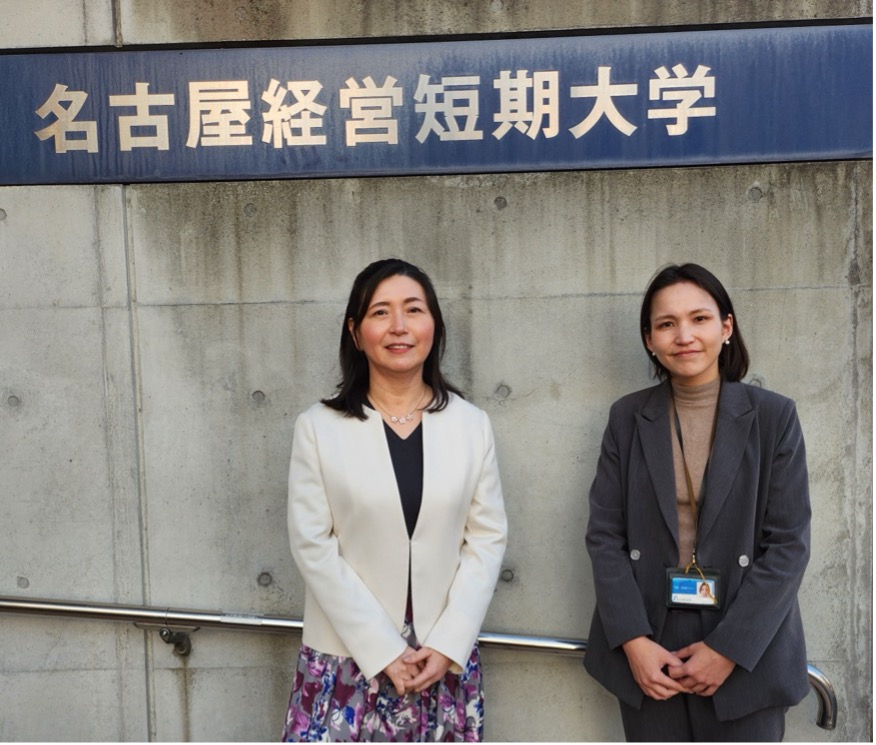 大藏純子准教授と亀尾百合香アメリー(Ed-tech総研協力研究員)。キャンパス内にて。ふだんから意見交換の機会を持つことも多いふたりの会話にはきょうも花が咲いていました。
大藏純子准教授と亀尾百合香アメリー(Ed-tech総研協力研究員)。キャンパス内にて。ふだんから意見交換の機会を持つことも多いふたりの会話にはきょうも花が咲いていました。
取材・文/森崎晃


