 松阪市立花岡小学校の授業の様子
松阪市立花岡小学校の授業の様子
2021年度を「松阪市GIGAスクール構想」元年と位置づけ、ICT環境の整備から利活用へと舵を切った松阪市。
コロナ禍の中を駆け抜けてきた2021年度の取組を振り返り、そこから見えた課題とは?さらに、今後に向けたロードマップについて、教育委員会の指導主事の方々にお話を伺いました。
先進校が蓄積してきた10年間の実績により短期間で全市での利活用が進む
2021年度に新たな教育大綱を示した松阪市。基本理念を「夢を育み 未来を切り拓く 松阪の人づくり」と掲げ、教育の情報化の基本方針として「新たなICT環境や最先端技術を最大限に活用することにより、個別最適な学びや協働的な学びを支援するとともに、変化の激しい社会で自分らしい生き方を実現するために必要な情報活用能力など、学習の基盤となる資質能力を育む」と謳っている。
国のGIGAスクール構想進行中に起きたコロナ禍。前倒しで補正予算がつき、大混乱の中、全国の自治体においてICT機器の整備が急ピッチで進められてきた。そのなかで2021年度を「松阪市GIGAスクール構想」元年(以下、GIGA元年)と位置づけた松阪市は、「整備から活用へのはじめの一歩」をテーマにICT利活用を戦略的に取り組んできた。
2020年12月までに、47の全小中学校に1人1台のタブレット端末(iPad)が完備された。家庭学習での活用を視野にLTEモデルを採用し、Wi-Fi環境がなくとも、格差がなく、いつでもどこでも使えるよう配慮しての決定だ。
「コロナ禍の対応を兼ねて、家庭でもオンライン授業が受けられる状態にすることを教育長が発信しました。そのことで、本市としてICT活用に何を求めているのか、全学校でイメージ統一ができました」(指導主事 楠本 誠氏)
緊急の対応であり、ICTを苦手としていた教員も少なくない状況でのスタートだった。それでも、自主的に校内研修を実施したり、教育委員会に講習をするよう依頼をしてくるなど、ICT利活用に向けた学校組織の団結や教員の意識の向上が見られたという。
「先生方は実にさまざまな工夫をされていました。例えば、自分のクラスだけでなく、学年で担当を振り分けたり、教科を越えて協力し合ったり、オンライン授業を複数のクラスで一緒に行うなどの取組が見られました。先生たちのプロフェッショナリズムの表れです。ICTを使う/使わないの議論ではなく、『あるもの』としてどう使うか、シフトが変わったと思います」(楠本氏)
コロナ禍という特殊事情があったとはいえ、なぜ松阪市の各学校が足並みを揃えてICT利活用のギアチェンジができたのか。その背景には、同市の三雲中学校が2011年度に総務省の「フューチャースクール推進事業」の実証校に指定され、10年以上前から1人1台タブレット端末を利用した授業実践をしてきた知見があったからだ。
「三雲中学校での先進的な取組を経験した先生方が、異動により現在は諸処の学校に在籍しています。その先生方はICTの利活用について、既に成功も失敗も体験されています。つまり、少し先の未来を経験した先生たちが、市内の随所にいることが本市の強みとなったのではないでしょうか」(指導主事 脇 清人氏)
「とりあえず使ってみる」からICTの効果的な利活用の模索へ
GIGA元年を振り返り、教育委員会が挙げる成果の一つは、市内の全47校で「とりあえず使ってみる」が達成できたことだ。これを同市では「アクティブ率」と呼び、それが前年比でかなり高くなったという。もう一つは、オンライン研修の導入により先生たちの要望に添った研修ができるようになったことだ。ICTの利活用が進めば進むほど、先生たちの疑問や知りたいことが増えていく。それに対し、従前は画一的な集合研修や、指導主事が各学校に出向いて行う研修だったが、オンライン形式の研修にすることで研修内容や受講形式やタイミングなどを臨機応変に対応できるようになったのだ。
こうした成果を通じて捉えている今後の課題が以下の3点だ。
1点は、先生たちが授業で積極的にタブレットを使うというアクティブ率は上がった一方で、ICTの利活用が授業のねらいや目的に結びついているのかの検証だ。個々の学習活動でICTを利用することが最適だったのか、学習場面によっては紙の教材の方が向いているケースはなかったか、本来の授業の目的を常に確認する必要があるということだ。
「アクティブ率に対し、ICTを使った結果、子どもたちの学びがどう変化したかを“完遂率”と呼んで、その評価と検証に今後取り組んでいく予定です」(楠本氏)
課題の2点目は、先生たちが1年間でICT利活用を積極的に進めた一方で、それが各学校内で閉じて完結していたことだ。オンライン利用によって距離や時間の制限なく誰とでもつながれる利点を活かし、学校を越えて教員同士がつながり、実践の共有への活用を期待している。
3点目はオンライン研修が始まったことでの課題だ。初めての試みでGIGA元年は臨機応変に対応してきたが、必要なものを精査し、従来からの教員研修にどう位置づけられるか、研修全体の見直しを図ろうとしている。
家庭学習の改革へ
個別最適化と協働的な学びをめざす
教育の情報化にとって大きなターニングポイントとなる2024年度。周知のとおり、小学校へのデジタル教科書の本格導入、全国学力・学習状況調査における児童生徒質問紙調査のオンライン化、そしてCBT化が計画されている。節目からの大きな変化に対応していくために、これからの2年間をどう取り組んでいくかが問われる。そこで松阪市では2024年度に向けたロードマップを作成中だ。「松阪市GIGAスクール構想」2年目の2022年度が勝負の年と捉え、3つの施策に注力していこうとしている。
第1に、教育大綱の基本方針でも挙げられた、ICTを活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の取組だ。そのなかで特に力を入れようとしているのが、家庭学習の改革だ。
「個別最適な学びと協働的な学びは、もちろん学校の授業の視点からも取り組みますが、大きく変えていきたいのが家庭学習です。例えば今までは、学校で宿題を出す場合に、みんなが同じ宿題を与えられてきました。スタディサプリやデジタルドリルなどを使えば、児童・生徒の理解度状況に応じて個別最適化された宿題が配信できます。また、学校での学びの振り返りを家に帰ってからオンライン上で行い、家にいながらそれを仲間と共有することもできます。タブレットの機能をフル活用することで、個別最適な学びを充実させ、そこで得た力で仲間との協働的な学びを活性化させることができると考えています」(楠本氏)
家庭学習改革はスタディサプリなどの導入による本格運用に向けて、現在準備を進めている。動画講座やデジタルドリルへの期待は、基礎基本の定着はもちろんのこと、自己調整学習ができるようになること、さらに子どもたちがデジタル教材を使うことにより、家庭で一人でも学べる方法を学ぶことだという。
GIGA2年目の施策の2つ目が、地域・保護者への理解の促進だ。松阪市ではタブレット導入前に、教育長が市内の全11中学校区に出向き、各校区の保護者に説明会を実施してきた。その際に、端末を整備することだけでなく、活用のルールの説明や、保護者が不安に感じていることに対して答えることを丁寧にやってきた。それでも、「ICTを使った教育で子どもたちは本当に変わる」ということを保護者が納得していなければ、協力の継続も危ぶまれる。
子どもたちの変化を知ってもらうには、学んでいる姿を保護者に見てもらうことが一番だ。授業参観できる機会を増やし、保護者の時代とは授業そのものが変わっていることや、子どもたちがいきいきと学んでいる様子に今まで以上に触れてもらおうとしている。
「授業動画なども制作し、こちらからも保護者の方々に向けて発信していこうとしています」(脇氏)
松阪市のホームページではICT導入の学校事例の映像を3月から掲載し始めた。子どもたちが教室で学んでいる様子や、先生たちがどんなねらいでタブレットを使った授業をしているかを動画で見ることができる。

松阪市のホームページには、ICTを有効活用することでさまざまな学校活動に変化が起きている市内の小中学校の事例が動画で掲載されている。学校関係者の参考になることはもちろん、地域や保護者にも、子どもたちの学びがどう進化しているかが伝わる。
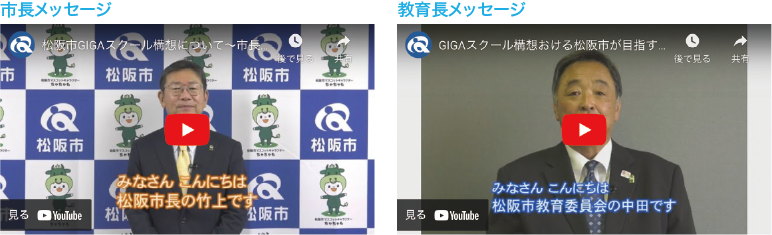
「松阪市GIGAスクール構想」について、市長からはICTを用いた教育の必要性、教育長からは、家庭学習での利活用の促進など、松阪市が目指す教育について、市民に向けてメッセージしている動画も掲載されている。
※松阪市ホームページ「GIGAスクール構想におけるタブレット端末の活用について」
10年前と変わらぬ先生たちの不安を蓄積してきた知見で解消を図る
そして、3つ目の施策が、教員研修の充実だ。今まで教育委員会が一律で行う教員研修は毎年夏休みに25講座開催してきた。そのなかでICTに関わる研修は2つしかなかった。しかし、ICTの導入にともない、先生たちの困りごとが多様化し、今までより多くの研修が必要とされている。一方で、オンラインで研修ができることもGIGA元年に体験したことから、今後は、教員自身の個別最適な学びを叶えるような研修を充実させることを検討している。
その背景に、同市の先進事例である三雲中学校で、楠本氏が10年前に研修主任を務めていたことがある。三雲中学校では、1人1台タブレットを導入して数カ月経ったときに、先生たちの感想アンケートを実施した。そこには先生たちの不安が散りばめられていたのだ。
「先生たちの思いを『10の不安』とカテゴライズしました。例えば、『ICTがなくても授業はできる』『使ったことがない不安』『新しい業務が追加される多忙感』などです。GIGAスクール構想が始まってから、初めてICTに取り組む先生方の意見を伺うと、10年前と不安はまったく同じでした。先生方は真面目だからこそ、不安に思うことは時代が変わっても同じなのです」(楠本氏)
三雲中学校の研修主任として楠本氏は、これらの不安を解消する策として、全員が時間をつくって集まる「全体研修」、空き時間や放課後に行う「有志研修」、そして日々の職員室での「雑談研修」の3つのパターンの研修でICTを浸透させてきた。特に先生たちの変化につながったのが、雑談研修だった。
「私は理科教員なので、理科の先生同士で、職員室で意図的に授業の話をしていたのです。大型モニターに授業内容を映しながらアプリの使い方などを相談してみたり。他教科の先生たちも授業方法には興味があるので、その会話を見聞きしてくれる先生が増えていきました」(楠本氏)
この経験がGIGA元年に、現場の先生たち一人ひとりの悩みに耳を傾けて、先生たちの気持ちに寄りそったオンライン研修を実施してきたことへとつながり、今後さらに充実を検討している。
教育活動を「再定義」し、選択肢を増やす
子どもたちを主語にした学習活動へ
2024年度に向けたロードマップを検討する際、楠本氏がカギとなると捉えたのが2022年度から高校で始まる「探究」だ。
「例えば、子どもたちが自己調整学習ができるようになるには、自分の理解度を俯瞰して見る力が必要です。でも児童・生徒に『自分の弱点は?』と聞いても答えられないと思います。いわゆる問題発見力と問題解決力を養っておかないと気づけません。それには、日頃から『なぜ?どうして?』という視点をもつことを当たり前にしていく必要があります。小中の9年間でしっかりと磨いていくことが、高校での探究の課題発見につながっていくと思います。ICTの利活用を検討する中で、探究の重要性に気づかされました」(楠本氏)
また、授業デザインにおいては、教員のマインドセットを変えることが求められるが、楠本氏はさらに“再定義”がキーワードとなると語る。
「ICTが入る前と後では、教育に関わるさまざまなもののあり方が変わってきています。昔の学校で“動画視聴”といえば教室に1台のテレビでNHKの教育番組を見ていたことぐらいです。しかし今は、1人1台の自分専用タブレットがあります。自分のペースで見たり、それぞれ別のコンテンツを見たりすることができるのも“動画視聴”なわけです」(楠本氏)
“授業”のあり方は今では無限にも感じられる。いかに再定義するか。再定義は、それぞれの活動の意味が変わるということではなく、広がっているイメージだ。それはつまり、選択肢が広がっていくということだ。
「選択肢の広がりは、これからの学びにとても重要です。選択肢があれば子どもたちは選べます。選ぶという行為は主体的なことです。すべてが選択ばかりでは収拾がつかなくなるため、制限された中での学びも必要ですが、選択できる割合が増えていくほど、子どもが主語の学習活動になっていくと思います」(楠本氏)

松阪市立花岡小学校の授業の様子
地域・保護者、産官学とともに取組を評価しながら新たな課題に向かう
ICTの利活用が進むことで、教育委員会にも学校現場にも次々と新しいミッションが発生してくる。例えば、市の「新たな学びの創造事業」として指定校に取り組んでもらうことや、個人の先生にICT活用方法を検討してもらう「開拓プロジェクト」、機器の設定や年次更新を担当する情報担当者会、大学や企業と研究を共にする連携協定などだ。進行中の取組も含め、新たに発生するミッションなどを振り返り、客観的に評価するために、GIGAスクール推進協議会をつくる計画もある。
「多数の取組をやりっぱなしではなく、企業さんや大学の先生、PTAの代表の方などにご参加いただき、ご意見いただくような場です。そこで取組の“完遂率”を評価いただくことで、次年度への取組につなげていきたいです」(楠本氏)
教育委員会が地域の産官学・保護者のハブとなって、子どもたちのより良い未来の学びを創造しようとしている意気込みの現れだ。
今後の展望について脇氏、楠本氏に伺った。
「ICT導入で今までにない学び方がフォーカスされがちですが、学校や先生方の従来からの取組の大切さが改めて問われている気がしています。本市のホームページでも紹介している飯高中学校では、ICT導入以前から地域をテーマにした探究活動が盛んで、そこに1人1台タブレットが入ったことで地域とのつながりや発信がさらに深まり広がりました。探究という学びとICTの相性が良かった事例です。こうした学校が市内で増えており、ますます広がっていくことに期待しています」(脇氏)
「大きな転換期に教員として、教育委員会として仕事ができることは大変なこともありますが、本当に変わっていっていることを目の当たりにできる貴重な経験だと感じています。これからも地域・保護者の方々と共に松阪市の教育を創っていきたいです」(楠本氏)

松阪市立飯高中学校の授業の様子
Interview

松阪市教育委員会の皆さん
(写真右から)事務局学校支援課 子ども支援研究センター 指導主事 楠本 誠氏、脇 清人氏
小学校教諭出身脇氏と中学の理科教諭出身の楠本氏。
「10年間、1人1台タブレット端末の取組をモデル校で継続できたことは、大きな財産です。その知見が、本市GIGAスクール推進のベースとなっています」(脇氏)
「ICT導入に対する先生たちの不安は、三雲中学の10年前も他校の今もまったく同じ。不安を取り除くには全体研修も大事ですが、雑談のなかでジワジワと気運をつくっていくことも、非常に効果的だと思います」(楠本氏)
●自治体プロフィール
人口:16万1,442人(2021年5月1日)
公立小学校:36校/児童数8,181名
公立中学校:11校/生徒数3,971名
三重県のほぼ中央に位置し、東は伊勢湾、西は奈良県に隣接。2005年に旧松阪市・嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町の1市4町が合併し新制・松阪市となった。国内最古の土偶が出土した粥見井尻遺跡を始め多数の遺跡があり、縄文時代から繁栄していた。松阪牛の産地として知られているほか、農業、漁業、自動車関連の製造業が盛んである。
●GIGAスクール環境
・導入端末 小学校・中学校/iPad
・児童・生徒用はLTEモデルを導入。Wi-Fi環境がなくとも使用できることで、格差をなくしている。
・2011年から三雲中学校が総務省「フューチャースクール推進事業」と文科省「学びのイノベーション事業」の実証校として、ICTを活用した授業に取り組んできた知見を元に、その取組が早くから市内全体に拡充されている。
発行:2022年3月
取材・文/長島佳子 デザイン/渡部隆徳、熊本卓朗(KuwaDesign)
